落乱47巻、鉢屋の店のお面が欲しくなったので、組頭の面の皮を作ってみました。
こないだのイベントで看板息子(?)してくれてたんですが、結構人目を引いてくれた模様。
身内には「こんなもんどうやって作ったの?」とか聞かれたりなかったり。
そんなわけでメイキング!
…の前に注意書き。
・お面作りなんぞやったこと無いまんま、調べもせずに見切り発車。
・張り子の要領で作れるんじゃないかなー?って思った。
・クオリティに期待したら負け。
OK?
準備したもの
・厚紙
・紙
・ゴム紐
・ハサミ
・ホチキス(正式名称忘れた)
・木工用ボンド
・あとなんか細々したもの
1.厚紙で顔の形をした骨組みを作る。
(写真取り損ねてたから裏側からで申し訳ない)

今回はたまたまあったティッシュの空き箱。
一センチくらいの細さに切ってから、ホッチキスでバチバチと。
穴のでっかいザル、もしくはカゴみたいなかんじ。
鼻の部分も適当に三角形を作って盛り付けてあります。
※本当は粘土や木で型を作った方がいいんだろうけど、
量産するものでもないし、紙なら終わった後に簡単に捨てられるので。
2.面の皮の下地を張り付ける。

紙(余裕があるなら障子紙など、薄くて繊維の細かいのが好い)を、
水で塗らして、一枚一枚盛り付けていきます。
まずは水だけ。ここ大事。
私はプリントしそこねたりして使えなくなった紙を使いました。
固い紙を使う場合は、くちゃくちゃにしてから伸ばして貼るといい…かも。
穴がないように二重三重に。
写真は顎のあたりがまだ途中。本当は全部にまんべんなく張り付けていきます。
水しか使ってないので剥がれやすいけど、我慢。
乾けばそれなりに固まります。
この状態で放置すると、「デスマスクだ!!」と家族に気持ち悪がられます。
3.面の皮の表面を重ねる。
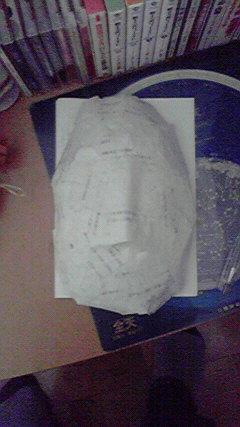
乾いた上から、今度は糊を使って紙を張り付けていきます。
糊は米粒で作ったのだとよくのびて張り付くけど、水溶きボンドで十分です。
普通の糊より薄めて(薄めないと乾いた後にカピカピになる)、刷毛などを 使って塗りつけます。
この表面がお面本体になるので、紙のツギハギとかは一応考えた方がいいかも。
私は紙が固かったので、水溶きボンドに浸す勢いでベショベショにしてから張り付けました。
刷毛も使わなかった。
皮膚を張る気分で三重〜五重に。適当に自分でちょうど良いと思ったらやめます。
4.骨と下の皮を、表皮とばらばらに外します。
ここで骨を外すために、最初の皮の部分を水だけで貼りつけました。
使うのは表皮だけなので、もう骨と内側の皮は捨てて平気です。
5.表皮のはじっこ部分を整える。
ハサミで切ったり、余った紙を折り込んだり。
かぶったときに直接皮膚に当たるのはこの部分なので、気になる人は念入りに。
6.塗る。

慎重派の人はあらかじめ薄いペンか鉛筆か何かで下書きをするのも有。
私は直に塗って案の定失敗しました。
絵の具は紙に合わせればいいんじゃないかな。
これはアクリル。使った紙が反古紙なので、水彩だと字が透けてしまうというだけの理由です。
目は描きにくかったので後から張りました。
写真は移動させながらバランスを見てるとこ。
目のふちや包帯部分は油性ペンで書き込みました。
包帯や布を貼っても良かったかも。
7.目の部分に穴を開ける。
キリや目打ちがあると便利だけど、別になくても平気です。
ど根性と慎重さと適当な刃物があれば十分です。
あけた穴が目立たないように、断面部分も瞳の色で塗るといいかも。
8.耳の辺りにゴム紐を付けて、完成!

ゴム紐は余ってた髪ゴム。百円しないで売ってるやつ。
紐を通すために穴をあけているので、その部分だけ布テープで補強してあります。
ちなみにこの組頭、片目しか開いていないので、かぶると視界が狭くて大変危険です。
そこまで考えてなかった…。
暇な時間を使ってちょこちょこ製作。
一日一時間×三日で、所要時間三時間くらいかな。
しかもミュんたまDVD見ながらとか、忍たま見ながらだったりしたから、実質はもっと短い。
紙や絵の具を乾かす時間の方が明らかに長いです。
鉢屋目指してしんべェ作ってみたいけど、輪郭が難しい…。
「こんなんだったら私の方が上手いもの作るぜ!!」って方、
是非とも作って私に見せてください!!
そんで作り方とか教えてほしいなぁ〜。
人の工作、完成品見るのも過程を知るのも大好きなんだ。